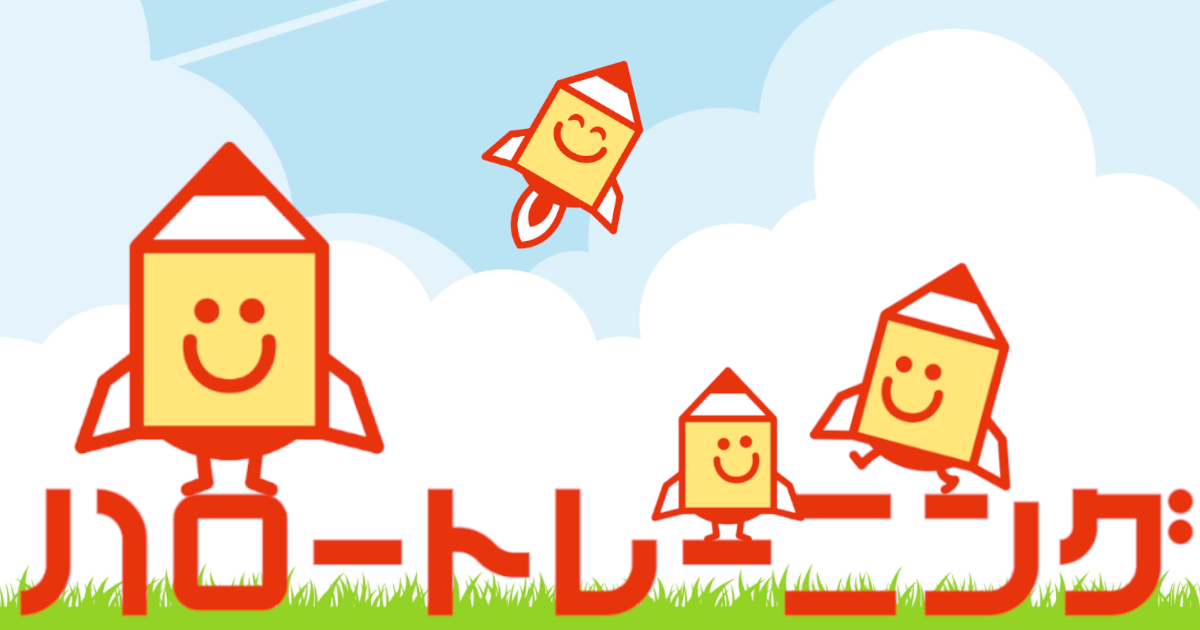前稿(下記参照)では、筆者自身の経験と、いささかの知見を踏まえて、50代の転職の「厳しい現実」について、本音とホントの事情をお話ししました。
▼晴れのち嵐・・50代の転職は厳しい。現実を直視し「新たな仕事観」を持って臨もう。
-

晴れのち嵐・・50代の転職は厳しい。現実を直視し「新たな仕事観」を持って臨もう。
この稿を書くにあたって、あらためて指折り数えてみたのですが、 筆者は、30年以上の社会人生活で6回転職し、転籍を含めれば計9社で働いてきました。 8社目の会社には10年以上在籍していたので、それで私の ...
ではどうやってその「厳しい現実」を乗り越えていったらよいのか、今回は、そこのところを中心に書いてみたいと思います。
もとより、シニアの転職に吹き付ける逆風を止めるすべはありませんが、風雨の中、ダメージを最小限に抑えて、リスクをできるだけ回避しつつ、とにもかくにも目的地にたどり着くために、何を考え、どのように前進していったらいいのかを書いてみたいと思います。
待てど海路の日和なし「ねらって当てにいく」スタンスで臨む
転職サイトなどを見ていると、「自分の市場価値」という言葉がさかんに出てきます。
転職マーケットの中で、募集企業がどれくらい自分を高く買って(評価して)くれるかの、人材としての商品価値という意味です。
転職もまた市場原理で動いており、需要と供給のバランスでニーズの有無・大小が決まるということ自体にはうなずけるものの、この言葉、私はどうも好きになれません。
言葉として多少デリカシーに欠けるということもありますが、それ以上に、この概念自体、一般化してとらえるには多少「レトリック」の匂いがするからです。
例えば、ドラッグストアにとって薬剤師は、第一類医薬品を販売するのに必須であり、処方箋処理数によって1店舗に何人と法令で定められていますから、ドラッグストア業界の採用マーケットでは、薬剤師免許の所持者は市場価値の極めて高い存在です。
他にも、看護師や建築士など特定の国家資格保持者は、いずれも業界内の転職市場において市場価値の高い存在と言えます。
また、経理や法務など、専門知識を要する専門職や、特定の技術や資格を有する技術者などは、同じく市場価値の高い存在と言えます。
しかし、技術や資格の縛りの無い、または、あっても希薄な職種に携わる人の場合は、希少性の大小によって採用現場のニーズが動いているのか、私は、いささか疑わしいと思っています。
私自身、過去に採用側として自社の中途採用面接を幾度も経験していますが、合否の判断の際、過去の履歴・実績には一応目を通していましたが、ほぼ全ての場合において「会社のカラー、組織の雰囲気に合う人物か」で採用を決めていました。
中途採用の面接のような極めて短い時間では、能力の有無は結局のところ測りきれませんから「合いそうか、合わなそうか」をもっぱら重視していました。
「転職は人脈」という人もいます。
私が面接した求職者の中には、たまに在籍社員の友人・知人がいましたが、当該社員の「推し」があれば、ほぼ全ての場合で「採用」としていました。
筆者は、そういった経緯もあって、ニーズが極端に少ない50代の転職市場で転職活動をする際、極めて重要なのは、自分と相性の良さそうな案件を嗅ぎ分ける「嗅覚」だと思っています。
もちろん、100%成功できるマーケットを見極めることが不可能なように、自分を確実に採用する企業を見極めることは不可能です。
しかし、「確度を上げる」ことはできます。
転職サイトの募集記事から読み取るのはやや困難ですが、細部のニュアンスと“行間“を客観的に注視すれば、企業が求めている人物の経験や年齢をおよそ推察することができます。
転職エージェント会社のアドバイザーは、企業が求めている人物像や経験、年齢などについて、採用担当者の「ホンネ」の部分を、営業担当や、場合によっては自身が直接採用担当者と会って把握しています。
関心を持った案件に関して、事前に相談できるアドバイザーがいるなら、確度はぐんと高まります。
関心のある企業を見つけるたびに、毎回、確度を検証し、企業に選んでもらうのではなく、「ねらって当てにいくスタンス」で臨んでいれば、仮に不採用になったとしても、その都度敗因の推測と軌道修正を行うことができますので、回を重ねるにつれ、確度は上がっていきます。
この際にも、転職エージェント会社のアドバイザーと接点を持っておくことは大いに役立ちます。
自分一人で転職活動をしていると、書類選考にせよ、面接選考にせよ、不採用の理由さえも定かではなく、自己弁護の気持ちも手伝って「結局年齢か」で済ませてしまいがちです。
もしアドバイザーから不採用の「実際の理由」を聞くことができれば、それが仮に「年齢」だったとしても、何かしら次のねらいを定める時の参考になります。
ちなみに、転職サイトには、登録しておくとヘッドハンターからスカウトを受け取ることができる、スカウト型の転職サイトがあります。
年代別のスカウト率は、そのサイトがどのような年齢・職種層の求職者をメインターゲットにしているかによって異なりますが、おおむね20代が40%程度、30代が50%程度であるの対して、40代はかなり減って10%程度、50代にいたっては総スカウト数の1%程度あれば良い方というのが実情です。
あくまで仮定の話ですが、30代の登録者全員に企業やヘッドハンターから届くスカウトメールの総数を全国で1日あたり5万件と仮定すると、50代の登録者に届くスカウトの総数は、全国合わせて1日1,000件程度しかないことになります。
しかもこの1,000件のメールの対象者には、IT人材や特定専門職、ハイクラス管理職が相当数含まれているとすると、その他の一般的な職種・役職に就いている50代の求職者1人に届くスカウトメールは、ほぼ無いに等しいということになります。
つまり、50代以降の転職活動は、ウエルカムな市場に対してエントリーし、自己の価値を問うのではなく、もともと閉ざされた扉を一軒一軒ノックして、自分を雇わないか尋ねて回るようなものだと思います。
こう言うと、身もふたもないように思われるかもしれませんが、この厳しさを覚悟して、腹を括って、粘り強く取り組むことが、50代以降の転職活動にとって何より肝心な心構えとなります。
書類選考で何度落とされようと「こういうものだ」という認識を持ち、自ら「ねらって当てにいく」主体性を失わずに臨む、それが自分自身を救う「転ばぬ先の杖」になります。
まずは「リファラル採用」の可能性を探ってみる
「リファラル採用」という言葉、昨今では多くの企業で使われているので、ご存じの方も多いかと思います。
「社員の紹介による採用」を意味し、以前は「縁故採用」「コネ採用」とネガティブなイメージで語られることも多かったのですが、現在ではむしろポジティブな採用手法として一般化しています。
企業にとっては、採用コストを削減するメリットがあり、求職者が事前に紹介者の社員から社風や業務内容について説明を受けているためマッチング率が高く、さらに、転職・採用活動のマーケットに出てこない人材を確保できるというメリットもあります。
多くの場合、若手社員の有効な採用手法として認識されているリファラル採用ですが、実は50代以降の転職においては、まず、このリファラル採用の可能性を探るのが、年収を極端に減らさず、職場環境や労働環境の点でも満足度の高い転職ができる最も有効な手段です。
リファラルというより「ツテを頼る」、という方がしっくりくるかもしれません。
とにかく、在職中から、同僚や上司、部下や後輩、親類や友人、取引先の担当者や、関係者などに、ことあるごとに再就職の話題を出してみることをおすすめします。
もちろん雑談としてで構いません。
相手からは「いい転職先が早く見つかるといいですね」程度のあっさりした対応しか返ってこないことが通例ですが、中には、何気ない雑談のつもりで話した相手から思わぬ誘いがあったり、また、まったく期待していなかった相手から「うちの取引先が人材を募集している」など想定外の話をもらったりして、結果それが再就職につながったりすることもあります。
肝心なのは、人任せにせず、自分で可能性の網を張ることです。
自分で動かずしての、棚からぼたもち的な話は、まず起こりえないと思っていた方が賢明です。
退職の報告ついでの雑談から想定外に話がつながって再就職先が見つかるということは、シニア世代の転職において意外によくあることで、50代の転職で、比較的スムーズに転職先が決まる場合の多くは、このツテ絡みであることは、ぜひ意識に留めておいてほしいと思います。
とは言え、人は自分の価値を過信しがちな生き物ですから、「今の環境の延長線上で勤め先を探さなくとも、新たな環境で自分のキャリアを評価してくれる企業がきっと見つかるはず」と思いがちなものです。
まったく新たな環境で、新たに自分を必要としてくれる人と場所を見つけて、心機一転頑張りたいと思うのは、むしろ自然な心情かもしれません。
ましてや「望まざる退職」であった場合には、「今の会社の同僚や上司・部下、取引先などにすがるのはまっぴら、プライドが許さない」という人も少なくないと思います。
また、リファラル採用がその人にとって「望ましい転職」なのかは、個々人のケースバイケースで、なんとも言えません。
筆者がかつて面識のあった50代の求職者の方で、懇意にしていた取引先から好条件で誘いがあり、リファラル採用で転職された方がいらっしゃいましたが、入社後、聞いていた内容と実際の仕事の相違が大きく、半年も経たずに退職されたと、後になってご本人から聞きました。
比較的少数ですが、そのような失敗例もあります。
それでも、リファラル採用による転職は、退職後の転職活動という、大きなストレスとリスクを回避できると言う点において、また、望ましい転職ができる保証があるとは言えない、シニアの厳しい転職事情を鑑みて、やはり、まず第一の選択肢として考慮・認識されておいた方が良いかと思います。
ただ、現実には、リファラル採用の可能性を探ったとしても、必ずしもそれが見つかるわけではありません。
意外に多くの人がリファラル採用で転職しているといっても、それより多くの人はツテ以外の転職方法を選ばざるを得ないのも事実。
そこで重要になってくるのが早い時期からの転職サイトの活用です。
転職サイトの早期活用で自分の置かれている状況が浮き彫りに
筆者自身の経験を踏まえて繰り返しますが、ツテに頼らないシニア世代の転職は、多くの場合、想定していた以上に厳しいものになります。
さすがに、20代、30代の頃のように「辞めてから考えよう」という方は、ほとんどいないと思いますが、リスクを考えると在職中からの「本気の」転職活動が必須と言えます。
そのためには、転職を決意した時点で、すぐにでも転職サイトに登録して、実際に転職活動を始めることが肝要です。
今の転職サイトは、webを介して求職者と求人企業、エージェント企業のアドバイザーや、人材紹介会社のスカウト担当者(ヘッドハンター)も含め、双方向、複数経路でのアプローチが可能になっており、利用してみればたちどころに、求職者としての自分が置かれている状況が否応なしに実感できる仕組みになっています。
しかも、在職時のタイミングで、転職サイトを活用すれば、リスクを取ることなく、これまで見えてこなかったものが如実に見えてきます。
今の会社を辞めて「食ってゆけるか否か」、それがたちどころにわかります。
場合によっては、退職を思いとどまるということもあるかもしれません。
「転職が厳しそう」という理由で退職を躊躇するようであれば、今の会社を辞めないことがベストの選択肢です。
20代、30代の転職とは違い「いざとなればどうにでも・・」ならないのが50代の転職、留まれるものならば、留まって正解です。
ただ、この世代になって転職を考え始めた方は、やむにやまれぬ事情があり、例え転職が厳しいとしても退職せざるを得ないという方が大半かと思います。
であれば、なおさら早期に転職サイトを活用することをおすすめします。
ちなみに、転職サイトに登録して転職情報を閲覧するだけでは、あまり得るものはありません。
見るだけでなく、実際に応募してこそ、自分の置かれている本当の状況が見えてきます。
また、「エージェントタイプ」の転職支援サービスに登録して、在職中から積極的に面談をこなしていきましょう。
エージェントから面談の案内が無ければ、自分から依頼する積極的な姿勢が大切です。
転職を決意し、しかも会社に退職の意思を伝えていない時期は、とにかく辞めることのみに関心が向かいがちで、ある意味「地に足がついていない」状態になりがちです。
転職を決意したら、退職に向かって行動するのではなく、1日も早く、今後の現実に向かって歩みを進めてください。
在職中からの転職活動で、首尾よく早期に転職先が見つかれば、それに越したことはありません。
「もっと厳しいかと思っていたら意外とスムーズだった」、物事がうまくいくときは概してそんなものだと思います。
尚、どの転職サイトに登録するのが良いかと言えば、使えそうだと思ったサイトには全て登録してみるのがベストです。
“50代の転職に有利なサイト” のような、都合の良い話は、はっきり言ってありません。
そもそも、転職マーケット自体、シニア世代に対する需要が極めて薄いわけですから、そこに特化したサイトは存在しません。
「ミドル」や「シニア」という言葉を冠したサイトは存在しますが、ミドルを冠したサイトのメインターゲットは30代から40代前半ですし、シニアを冠したサイトの掲載案件は、なり手が常に不足している業界、会社の案件か、派遣などの非正規雇用が中心で、そういった求人は他のサイトにも載っていることがほとんどです。
無論、ミドル、シニアを冠したサイト自体を否定するものでは決してありません。
これらのサイトも併せて活用してみることはおすすめしますが、それのみでは不十分です。
“1パーセント”の狭き門をなんとか潜り抜けられるように、できるだけ多くの転職サイトに登録し、できるだけ多くの案件に目を通しましょう。
登録の優先順位としては、公開・非公開を合わせた求人案件数が圧倒的に多い、大手の転職支援サービス・転職サイトから登録を始めることをおすすめします。
次項では、転職支援サービスの種類と内容、それぞれの代表的サイトを紹介します。
タイプ別に見る転職支援サービスの特徴と活用法
転職支援サービスは、その業態によっていくつかのタイプに分けることができます。
それぞれが自社のサイトを展開しているため、十把一絡に「転職サイト」とい括りでとらえられがちですが、
タイプによって、サービスの目的や、ユーザーへのアプローチの仕方がだいぶ異なります。
エージェント(人材紹介)タイプ
まず最初は「転職エージェント」です。
「エージェント」という故障でよく知られていますが、業態としては「人材紹介事業」になります。
人材紹介事業は、厚生労働省が認可する許可事業で、求人企業・団体と、求職者双方の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんする事業形態です。
採用成功時に求人企業から紹介手数料を受け取ることで事業を行っており、求人情報の紹介はもちろん、転職活動に関する相談・アドバイスや、職務経歴書など提出書類の添削、模擬面接、面接スケジュールの調整、入社後の年収額の交渉など、転職活動全般の支援を行うのが特徴です。
採用が決定してはじめて収益が発生するため、内定の可能性が低い50代以上の世代の場合、面談の案内すらない場合もありますが、そうした場合でも、こちらから面談を依頼するなどして、「転職活動の支援をしてくれる」というエージェントの特色を積極的に活用しましょう。
転職エージェントは、味方にしておいて損はない、否、50代の転職活動を乗り切るためには、ぜひ味方しておきたい存在と言えます。
エージェントタイプのメリット
◎転職サイトには公開されていない「非公開求人」を多数扱っている
◎募集記事には載っていない採用企業の情報や、第三者目線での評価を聞くことができ、内定を得るためのアドバイスが得られる。
◎基本的に求職者が入社した際の年収額に応じた報酬額を事業収益としているため、年収交渉などでも心強い味方となってくれる
エージェントタイプのデメリット
⚪︎アドバイザーのパーソナリティーやキャリアによって、相性が合わないことや、適切なフォローを受けられないことがある
⚪︎内定の可能性が低い人材と見られた場合、対応が極めて手薄になることがある
⚪︎そもそもシニア世代の場合、案件紹介を全くしてくれない(シニアが対象の案件を持っていない)エージェントがある
代表的なエージェントサイト
◉リクルートエージェント
◉doda(他タイプとの複合型)
◉JAC リクルートメント
求人広告掲載タイプ
求人情報を自社のサイトに有償で掲載し、求職者を集めるサービス。
広告掲載料で事業が成立しているため、基本的に求職者へのサポートは無いのが通常です。
求職者は、ウェブサイトに掲載された求人を自発的に閲覧し応募フォームを使って直接企業に応募します。エージェントへの成果報酬と比べて広告掲載費用は安価のため、業種や職種、会社規模、採用ポジションなど、多種多様な求人が数多く掲載されているのが特徴です。
ただし、掲載案件の大半は若手・中堅社員の採用を目的としているので、シニア世代は、ほとんどの場合、書類選考で不採用となります。
「企業があなたに興味を持っています」などの「気になるメール」が頻繁に届きますが、これは、求人企業があらかじめ選択した業種・職種などのワードと、求職者の登録内容が合致した場合、機械的にに抽出し送信されているものです。
また、求職者の経歴と企業の募集要件が合致すれば「応募をお待ちしています」などの「オファーメール」が届くこともありますが、求職者の年齢は、エントリー前は求人企業に非公開であるため、オファーをもらって応募したとしても、書類選考で門前払いになることは日常茶飯事です。
とは言え、中には書類選考を通って面談まで行くケースもありますので、案件のまめなチェックとエントリーは欠かさず行う必要があります。
エージェントからの紹介やスカウトメールが皆無で、状況が八方塞がりに見える時は、唯一の「頼みの綱」にもなります。
求人情広告掲載タイプのメリット
◎多種多様な求人情報を閲覧でき、直接企業に応募できる
◎良きにつけ悪しきにつけ、自分のペースで誰からも意見されず、自分の判断だけで転職活動ができる
◎「どこからも、何のアプローチも無く、活動がストップしてしまう」という状況を回避できる
求人広告検索タイプのデメリット
⚪︎案件の大半は20代・30代を対象とした求人(年齢制限を明記しての求人は法律で禁止されている)のため、エントリーそのものが無意味である場合も少なくない
⚪︎自己完結の転職活動のため、第三者の的確な意見、アドバイスが得られない
⚪︎原則フォローは皆無なので、面接スケジュールの調整も、年収に関する交渉も、全て自分で行う必要がある
代表的な求人情報検索サイト
◉リクナビNEXT
◉doda(他タイプとの複合型)
スカウトタイプ
求人企業や人材紹介会社の担当者(ヘッドハンター)が求職者をスカウトするためのプラットフォーム(求職者情報データの提供およびコミュニケーションツール)を提供し、データベース利用料や紹介報酬を得るサービス。
スカウトの対象となる人材がターゲットのため、おもに、技術系専門職や管理系専門職、経営層などのいわゆるハイキャリア人材が対象となります。
ハイキャリア人材の中でもさらに業種・職種に特化したアプローチを行っているサイトもあります。
一般的な求職者の場合、サイトに登録したとしても、企業からも、ヘッドハンターからも、サイトの運営会社からも何の音沙汰も無いことは珍しくありません。
とは言え、スカウトは常に、〇〇企業の〇〇セクションの〇〇のポジションで、求められるスキルは〇〇という、具体的な案件とのマッチングを念頭に行われますので、かならずしも衆人が認めるハイキャリアの持ち主である必要はなく、自分のスキルや経歴にピンポイントで合致する案件が出てきた場合には、スカウトが来る可能性もあります。
その可能性に期待し、ひとまず代表的なサイトには登録しておくのが良いかと思います。仮にスカウトが全くこなかったとしても、「現実を直視し自己幻想から脱却するため」と、割り切るくらいの気持ちで活用されることをおすすめします。
スカウトタイプのメリット
◎スカウトの対象となるスキル・経歴があれば、年収アップなど高条件での転職が可能
◎自分のキャリア・履歴を提示して引き合いを待つ、「待ち」の転職活動ができる唯一の手段
◎ヘッドハンターと接触することにより、転職活動に有益な知見を得られる
スカウトタイプのデメリット
⚪︎スキル・経歴がスカウトの対象にならない限り、何の反応も得られない
⚪︎公開求人は少な目のサイトが多く、自分からアクションをかけるにはあまり適さない
⚪︎登録してただ待っている状態を「転職活動をしている」と勘違いしがち。
代表的なスカウトサイト
◉ビズリーチ
◉リクルートダイレクトスカウト
◉doda X
◉enミドルの転職
次回は、筆者が実際に利用した転職サイト、転職エージェントについて紹介します(下記参照)。多くの方が利用する代表的な転職メディアを中心に、全て筆者が実際に利用しての所感を書きました。転職サイト選びの参考にしていただけたら幸いです。
▼50代の転職で、最低限これだけは利用すべき転職サイトはコレ!
-

50代の転職で、最低限これだけは利用すべき転職サイトはコレ!
前稿(下記参照)では、提供しているサービスのタイプ別に、転職サイトにはどのような種類があるのかを説明しました。 ▼50代の転職に立ちはだかる「1パーセントの関門」を乗り越えるために。 今回は、主な転職 ...
最後までお読みいただきありがとうございました。
【追記】
尚、長期化しがちなシニアの転職活動において、経済的な支えとなる「失業保険」の離職理由についてのお話し、および、失業保険をもらいながら受けられるハローワークの「公共職業訓練」の紹介を記事(下記参照)にしていますので、よろしければ参考にしていただければと思います。
▼シニアの早期退職には死活問題! 失業保険の手続きで、実は「会社都合」の離職理由になる長期残業の該当範囲とは?
-

失業保険の手続きで「会社都合」の離職に認定されるための条件とは。その思い込み、間違っていませんか?
先日、約20年勤めた会社を辞めました。 退職を決意するに至る過程が、なかなかシンドかったものですから、退職が決まってからは、胸のつかえが取れたと言うのでしょうか。それまでの曇天が快晴に変わったかのよう ...
▼失業保険をもらいながら職業訓練を受ける10のメリット【給付期間延長・受講手当支給・交通費支給など】
-

失業保険をもらいながら職業訓練を受ける10のメリット【給付期間延長・受講手当支給・交通費支給など】
転職を決意し、希望の持てる新たワーキングライフに向かって舵を切ったとしても、そうそう簡単にはいかないのが、生活の糧を得るための再就職の件です。当座は失業給付(失業保険)でなんとか凌げますが、そのまま漫 ...